
大学職員 小西 民恵さん
創発科学研究科 修士課程
創発科学専攻 (工学系領域)
2023年度 修了
現在の仕事内容について教えてください。
現在、医学部管理課経理係において、主に科学研究費補助金の機関経理、授業料等の現金収納に関する処理、給与・共済組合の連絡業務に関することを担当しております。
ありがとうございます。大学院に入学した背景はなんでしょうか?
大学職員になってから10年ぐらい経過した後、漠然とこれからのキャリアを考える上で新たな知識を取り入れる必要があるな、とは感じていたのですが、なかなか行動に移せておりませんでした。
2021年10月に事務職員大学院研修の公募があり、2022年4月から新たに設置される研究科である創発科学研究科では、ユニットを問わず複合的なカリキュラムで学ぶことができることに魅力を感じて受験を希望しました。
在学時の研究内容について教えてください。
創発科学研究科・危機管理学ユニットで、自然災害をはじめ、あらゆるリスクによって組織が致命的な状況になることを回避予防し、万一ダメージを負った場合にも被害を最小限にするような計画策定の手法を学び、「ローコードツールを用いた香川大学BCPのための初動対応支援」の研究に取り組みました。具体的には、大学BCPの継続的な更新がおこなわれない問題に対処するために、ローコード開発ツールを用いたアプリ開発を通じて初動対応の支援をおこないました。香川大学BCP(Business Continuity Plan:BCP)の実効性向上のためのシステムを内製開発し、非開発者の職員がアプリ開発をおこなうことでBCM(Business Continuity Management)を機能させる仕組みを検討しました。
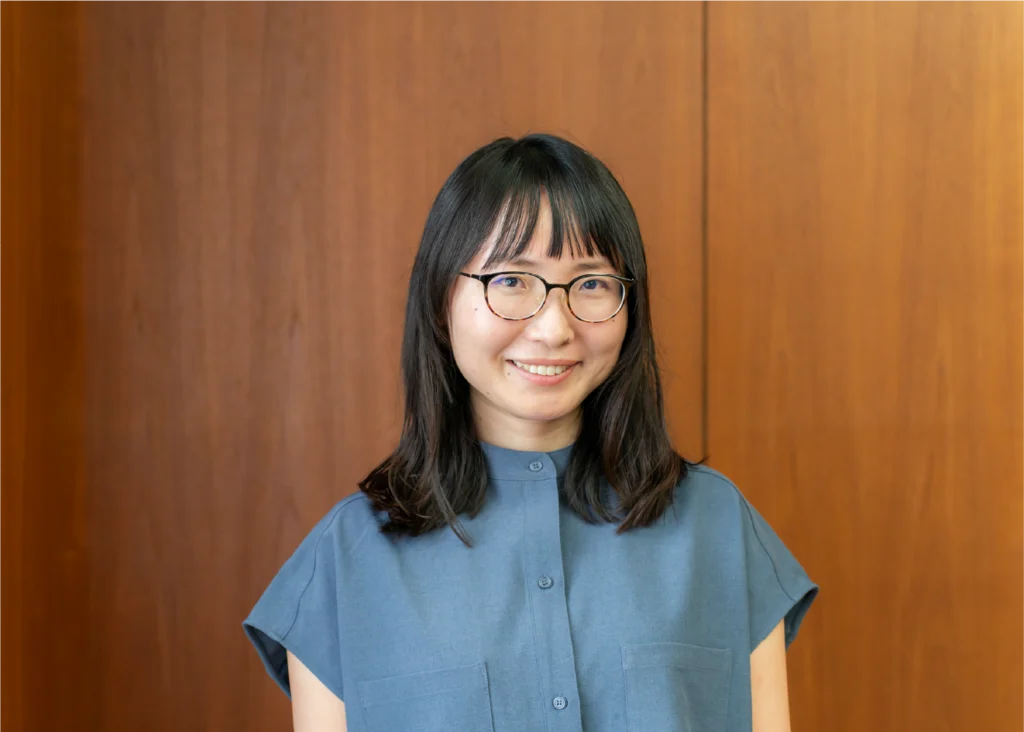
小西さんが感じている研究科の魅力は何ですか?
創発科学研究科はユニット制なので、私の場合は危機管理学を専門分野として選択した後、興味がある他の専門分野のユニットの講義を選択することができました。
主ユニットの危機管理学に軸足を置きながら、情報システム・セキュリティの専門分野を学び、異なる専門分野の教員からご指導いただく機会も多々ありました。
また、大学院はディスカッションメインの講義も多く、その中で他のユニットの学生と一緒になる機会もあり、それぞれ主ユニットが異なると、もともとのバックグラウンドにある専門領域が異なるので、180度違う見解を示してくれたときは、とても刺激をもらいました。
中でも、地域マネジメント研究科と連携した創発の実践という集中講義の中では、関心のある社会課題テーマを提起して、学生と一般の社会人の方がチームを編成して、課題解決に向けての解決策を検討し、提案までおこなったことは、とてもいい経験になりました。
素晴らしいですね!よい経験になったと思います。では、小西さんが感じている大学院の魅力を教えてください。
私自身は他大学出身で、大学時代は法学部で学び、労働法のゼミに所属していました。これまでのバックグラウンドは文系でしたが、社会人経験を得た後に、創発科学研究科のカリキュラムの中から現在自分が興味関心を持つ専門分野を選択することができて、本当によかったと思います。
教育研究機関で勤務しておりますので、自身で研究テーマを決めてデータを収集して、システム開発・検証の一連のプロセスを経験できました。この経験は、事務職員として教育研究支援業務に携わる上で非常に役立っています。

ありがとうございます。最後に、入学を検討している方へのメッセージをお願いいたします。
社会人の方でこれからまた新たに学びたいという意欲をお持ちの方でしたら、ぜひ創発科学研究科への進学をご検討いただけると幸いです。
学生時代に学んでいたことを社会人になってからさらに深めたいという方も、私のように学生時代とは全く異なる専門分野を学んでみたいという方もマッチするユニットがあるはずです。
研究テーマが定まらない場合は、リキャリスキル教学センターのスタッフへご相談いただくといいかなと思います。
研究を進める上で、研究室の選択、指導教員との事前協議はとても大切なことだと思っています。私も入学願書を提出する前は、受入教員の伝手はなく、リキャリスキル教学センターのスタッフに面談の機会をいただいて、後の恩師と出会うことができました。
職場を離れて、大学院生活での教員や学友とのゼミでの議論、たわいのない会話も含めて貴重な時間を過ごすことができましたし、この時のご縁は修了後も続いています。